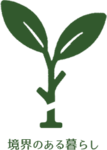- home
- 子育てと境界
子育てと境界
壊れる前に今の関係性を見なおす
子育ての悩みの多くは、子どものためにと思って頑張るほど深まっていく矛盾を含んでいるのではないでしょうか。
*怒りたくないのに、つい怒ってしまう
*少し距離を置きたいのに、実際には置けていない
*いい親でありたいのに、できていない自分を責めてしまう
こうした行き詰まりは、感情や性格の問題として片づけられがちです。けれど私たちは、それを 関係性の構造がもたらすもの と考えています。
親子の間に疲れや衝突が生まれるのは「どう関わるか?」という表面的な行動の前に、 境界のあり方そのものが整っていないこと が大きな要因です。
本稿では、子育ての日常に潜む3つのすれ違いを取り上げ、その奥にある構造のズレを見ていきます。そして、境界を引き直す視点を通して、関係を捉え直す試みを紹介します。
「どうすればいいか」という正解探しではなく、いまの関係がどのように成り立っているかを見直すこと。その視点の転換こそが、 無理のない関わりを取り戻すきっかけ になるのです。
応えることが限界を超えるとき
小さな子どもは、いつも「いま!」「すぐ!」「見て!」「やって!」と求めてきます。
親としては、それに応えることで関係がうまくいっているように感じるかもしれません。
けれど、すべてに応えなければならないという構造は、いずれ親子のバランスを大きく崩してしまいます。なぜなら、 子どもが求めることと、大人が応えられる範囲には必ずズレがある からです。このズレを無視して応じ続けると、大人は次第に疲れを溜め込みます。
やがて疲れがピークを迎えると爆発してしまうか、あるいは自分を消して応じることを「子どものため」と思い込み、当たり前にしてしまうか。そのどちらかに陥りやすくなるのです。
ここで必要なのは「いまはできない」「あとでやるね」と、 大人の都合も含めた対応を選ぶこと です。
親は親として、どこまで引き受けるのかを自分で定め、境界を引き直すことが大切になります。これは拒絶ではなく、 関係を持続可能にするための区切り です。
さらに、その境界をやさしく言葉にして伝えることで、親は自分を犠牲にせずにすみます。同時に子どもにとっても 「待つ」という新しい学びの機会 が生まれるのです。
自分で考える機会をつくる
子どもと接していると「こうした方がいい」「これはだめ」と、正しさを伝えたくなる場面は少なくありません。けれども、それが積み重なると、子どもは親の言うことを正解として選ぶようになり、 自分で考える機会を失ってしまう ことがあります。
そのような環境に残るのは、親から子へ一方的に価値判断が流れるだけの構造です。
子ども自身の判断を育むために必要なのは、 すぐに答えを渡すことではありません。
「あなたはどう思う?」「どう見える?」と問いかけることで、子どもが自分なりに考える時間と機会を持てるようになります。
大切なのは、親の価値観と子どもの考えの間に、健やかな距離を保つことです。
判断を押しつけるのではなく、別々の考えを尊重し合える環境をつくることが、 自然に自立した思考を育てる土壌 になります。
ここで言う「境界を引くこと」は、相手を拒むことではありません。自分の考えや営みを大切にするからこそ、相手を尊重できる。その姿勢が、干渉や押し付けに頼らない関係のあり方を育てていくのです。
離れることも関係の一部
子どもに寄り添い、一緒に過ごすことは、肯定的な価値として語られることが多くあります。
けれども、ときにそれが「ひとりでいることを許さない構造」に変わってしまっている場面が見受けられます。
「常に見て」「常に応じて」「常に並走して」。
そのように 切れ目のない関係 が続くと、子どもの自立の機会を奪うだけでなく、親自身が孤立してしまうことにもつながります。
親子関係に必要なのは、 つながっていながらも、完全には混ざり合わない関係 です。
たとえば
*別々の空間で過ごす時間をあえてつくってみる
*安全が確保されている範囲で、あえて失敗を経験させてみる
これらは放置や拒絶ではありません。「わざと離れてみる」ことで、それぞれに考え、感じる時間を持たせるということです。
むしろ、それは お互いの時間を大切にする境界の意思 につながります。
そして、その環境が自然に受け入れられるようになったとき、 親にとっても子にとっても有意義な時間 へと変わっていくのです。
関係性を保つための再設計
子育ての中で「境界を引く」というと、冷たくすることや突き放すことだと思われがちです。
けれど本当は、境界があるからこそ、関係性は壊れずに続いていくのです。
*全部を引き受けるのではなく、引き受ける範囲を決める。
*正しさを押しつけるのではなく、自分で考える機会を作る。
*常に一緒にいるのではなく、ひとりの時間をわざと設ける。
どれも、構造の設計としての境界のあり方です。
この視点を持つだけで、子どもと関わる時間が、少し呼吸しやすくなるのではないでしょうか?
ただし、ここで紹介したのは、すべての状況に当てはまる正解ではありません。
ひとつの関係のつくり方としての選択肢のひとつとして、あなた自身の感覚と状況に照らしながら、必要に応じて選び取ったり、手放したりして自分なりの境界の在り方を模索してみて下さい。