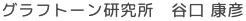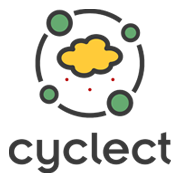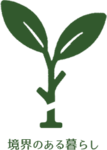- home
- 私たちについて
私たちについて
「境界のある暮らし」から、私たちの関係性を編みなおす
名前に込めたこと
グラフトーン(Graftone)という名前には、私たちが信じるつながりのかたちが込められています。
graft(接ぎ木) は、異なる植物同士が、互いの違いを失わずに、一部をつなげて、新しいかたちで生きていく技術です。
私たち人間もそれに見習って異質なもの同士が、無理に同化することなく、それぞれの根や葉を保ちながら、新たな命をともに育んでいく。
tone(音・響き) は、そうしたつながりのなかで生まれる、言葉にならない感覚(違和感)や、空気のニュアンス、微細な感情のやりとり。
私たちはちがいを保ったまま響きあう状態に、これからの社会や関係性のヒントがあると考えています。
強く主張しすぎず、しかし消えもしない。
同化ではなく、共鳴。
同調ではなく、余白。
そんな 半分でつながる在り方 を、この名前に託しました。
はじまりの違和感
誰かのために動いているはずなのに、ふと自分のことがわからなくなる。
まわりに気を遣いすぎて、気づけば言いたいことを言えないまま終わっている。
やさしくありたい。理解したい。つながりたい。
その願いのなかで、自分の輪郭がじわじわとにじんでいくような感覚がある。
それでも私たちは、 よかれ と思って・・・ 大人 だから・・・ 親 だから・・・ プロ として・・・といった言葉をよりどころにして、感じているはずの違和感にフタをしてしまう。
けれど、その フタをした違和感 こそが、社会の構造や関係性のかたちを見直すための、手がかりなのではないか?
そう思ったときグラフトーン的思考という構想が動きはじめました。
私たちの思い
グラフトーンは、答えや正解を導き出すための場ではない。
同時に、問いそのものを際限なく繰り返すことだけを重んじているわけでもない。
たとえば、こんな問いがある。
*やさしさと自己犠牲のあいだに、どんな境界を見いだせるのか?
*本音を言わないほうがよい空気は、どのように立ちのぼってくるのか?
*わたしの正義と、あなたの正義がすれちがうとき、どこに立ち直れる余白があるのか?
*「ちゃんとすること」に疲れたとき、人はどのように生き直せるのか?
*境界を引くことが、孤立ではなく自由や安心につながるのはなぜか?
これらはすぐに答えの出る問いではない。けれど、その都度「今はこれが最適だ!」と思える考えにたどり着くことがある。
しかしまた、時が経てば、「もう最適ではないかもしれない・・・」と違和感として立ちあがることもあるだろう。
その揺らぎを、常に当たり前にすることなく 変化の兆しとして受けとめられる研究機関 でありたいと願っている。
グラフトーンの役割
実践と思索を往復しながら、関係のかたちを編みなおすために
私たちは「思想」「実践」「関係性の設計」「学びと育成」の4つの軸を横断しながら、日常に潜む違和感を起点に、関係性の在り方そのものを再構築していく、応答的実験体としてこの場を開いています。
▷ 思想の探究
言葉を編みなおすことで、見えない構造に輪郭を与える
境界、ケア、感情労働、対話、制度などをテーマにした、独自の概念構築
哲学・社会学・臨床・教育といった知の体系と、日常の感覚を媒介する
note・書籍・連載などを通じて、構造と感受性のあいだに言葉を立ち上げる
▷ 日常の実験
暮らしの場から、仮説をかたちにしてみる
家族、職場、教育、地域など、具体的な関係の現場でのプロトタイピング
対話のルールづくり、制度の設計、相互ケアの仕組みの試行錯誤
うまくいったこと/いかなかったことの両方を、知のかたちとして共有する
▷ 関係性の設計
「わたし」と「あなた」のあいだに、無理のない距離をつくる
実践者・研究者・表現者が、互いの境界を尊重しながら協働するしくみの構築
オンライン/オフラインでの対話イベント、フィールドワーク、共創型の場の開催
小さな輪が重なっていくことで育まれる、ネットワークのあり方の探究
※「つながること」そのものを目的化するのではなく、関係の設計そのものに目を向ける
▷ 学びと育成
感受性を耕しながら、問いつづける技術を身につける
境界について学びなおすための連続講座、リトリート、企業研修、講演などの実施
知識の獲得ではなく「問いをもちつづける力」と「実践に翻訳する力」を育てる
肩書きや立場を超えて、気づき合い・育て合う共同体としての学びの場のデザイン
私たちが大切にすること
問いに開かれていること
正しさや完成ではなく、揺れや未完成をそのまま受けとめる姿勢。
ちがいを尊重すること
同じ言葉で語り合えなくても、それぞれの「異なる生」を肯定すること。
否定ではなく接続を選ぶこと
誰かを「わるもの」にせず、構造に目を向け、可能性を編みなおす視点。
小さな実践からはじめること
大きな変革ではなく、暮らしの単位から世界をゆるやかに更新すること。
感受性を知として扱うこと
数値にはならない感覚や感情を、大切な手がかりとして扱う態度。
これから、ともにつくる
この研究所は、完成された答えを共有する場ではありません。
むしろ、これまで見過ごされてきた感覚や小さな違和感を出発点に、世界の見え方を、少しずつ変えていくための、ゆるやかな実験空間です。
だからこそ、あなたの
「まだ言葉になっていないけれど、ずっと感じていたこと」
「こうじゃないと感じていたけれど、うまく言えなかったこと」
そんな感覚が、この場所を育てる種になります。
問いながら生きる人たちと出会いながら、ともに「境界のある暮らし」を少しずつ、社会に根づかせていきたい。
まずは、小さなことから。
声にならないものに、耳をすますところから。
ともに、始めていきましょう。
グラフトーン
設立メンバー一同

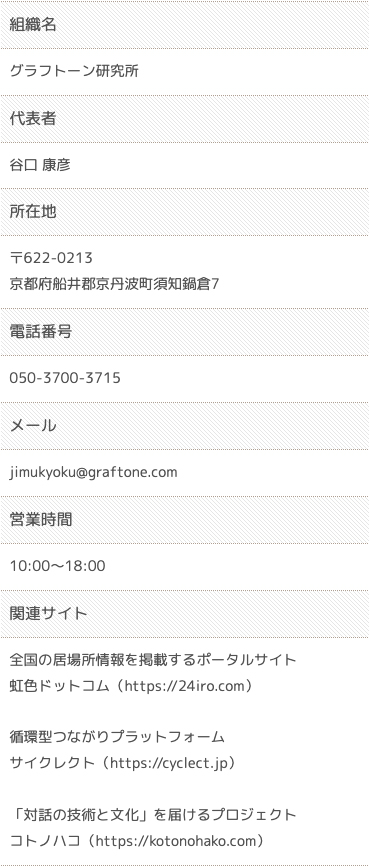

創設者のご挨拶
ようこそ、グラフトーンへ。
私たちは「人は境界のある暮らしの中でこそ自然に育つ」という仮説をもとに、この場を立ち上げました。
社会の中では、正しさや効率ばかりが優先され、知らぬ間に誰かを変えようとしたり、結果を急ぎたくなることがあります。
けれども、人が本当に変化するのは、強制や評価の外にある、余白をもった関係性の中だと思っています。
このラボでは、誰かに答えを渡すことはしません。
私たちは「半分だけ差し出す」ことを大切にしています。
教えるよりも、自分で考えられる構造を構築する。
支えるよりも、そっと離れて試せる環境を構築する。
その積み重ねの中で、人と人のあいだに本来の学びが生まれると信じしています。
ここに訪れたあなたも、ご自身のペースでこの場に触れてみてください。
そしてこの小さな出会いが、次の実践の始まりになるかもしれない不思議体験をぜひ感じてみて下さい。