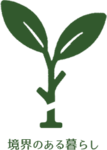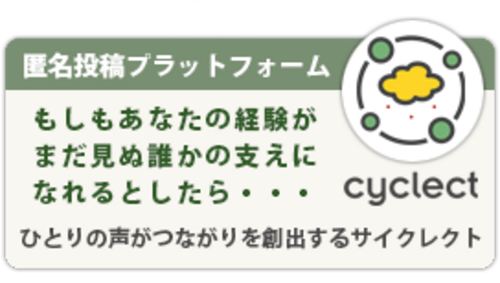- home
- 境界のある暮らし
境界のある暮らし
自分を閉じずに、他者と出会うということ
人と人が共に在るとき、そこには必ず、目に見えない「境界」が生まれています。
それは、物理的な距離ではなく、 関係性の中でお互いをどう扱うか という、非常に繊細な線引きのことです。
私たちが「境界のある暮らし」と呼ぶこの在り方は、誰かを遠ざけるための壁をつくることではなく、 互いが互いとして在れるための間を大切にする態度 のことを指します。
境界を語ることは、決して特別な状況や職業に限った話ではありません。
家庭での会話、職場でのやりとり、学校、SNS、パートナーとの関係……。
どんな場所でも、私たちは日々、 無数の境界に触れながら生きている のです。
そしてその境界は、多くの場合、あまりにも曖昧で、無自覚なままに踏み越えられたり、閉じすぎてしまったりします。
それが、誤解や遠慮、支配や依存といった形で関係に影を落とす。
つまり、 関係のしんどさの多くは、境界の在り方に起因している のです。
境界とは何か
「見えない線引き」の役割
境界という言葉を聞くと「線を引く」「距離を取る」「入ってこないで」というイメージを持つかもしれません。しかし私たちの考える境界は、単に分けるための壁ではありません。
自分が自分として立ち上がるための空間を保つもの 。
そして同時に、 相手を相手として尊重するための条件 でもあります。
たとえば、誰かに相談をされたとき。
よかれと思ってすぐに答えを返したくなるけれど、その前に一度「この人はいま、答えを求めているのだろうか?それともただ、聞いてほしいだけなのか?」と立ち止まる。
この一呼吸の間に、境界の感覚が宿っているのです。
「自分と相手は違う存在である」
この当たり前の事実を、どれだけ繊細に感じ取れるか。
それが、関係性の質を左右します。
優しさや親切にひそむ境界の曖昧さ
境界の難しさは、「善意」のふりをして、簡単に侵犯されてしまうところにあります。
たとえば、「困っているみたいだったから助けた」「何も言わないから、大丈夫だと思った」。
一見、優しさに見えるふるまいの裏に、 勝手な解釈や操作的な関与 がひそんでいることもあります。
本当に相手のためを思っているのなら、その人の声に耳を澄まし、その沈黙さえ尊重するはずです。
つまり、 優しさとは、踏み込むことよりも踏みとどまることに宿る のかもしれません。
しかし現実には「してあげる」ことで自分の存在価値を確かめたくなったり「わかってあげたい」という気持ちが空回りしてしまったり……。
気づかないうちに、 境界を曖昧にする行動 を取ってしまうことは誰にでもあります。
境界とは、思いやりや共感と同じくらい、 信頼と自律を土台にした関係を築くために必要な感覚 なのです。
閉じる境界とひらかれた境界
自分を守るための「閉じる境界」と
出会いなおすための「ひらかれた境界」
「境界を持つ」というと、冷たく感じる人もいるかもしれません。
たしかに、ときに私たちは、傷つかないように自分を守るため、 閉じた境界 をつくります。
それは自分を保つために必要な反応であり、決して否定されるものではありません。
けれど、そのままでは、誰とも本当の意味で関わることができなくなってしまう。
一方で、必要な場面では、自分の内側にあるものを差し出し、 ひらいた境界 を持てることが大切になります。
ここでの“ひらく”とは、無防備になることではありません。
どこまで差し出し、どこからは留めておくのかを、自分で選び取れる状態 。その選択の自由こそが、私たちが「境界のある暮らし」と呼んでいるものの核心にあります。
いつも側にある境界の暮らし
境界のある暮らしは、日常の中でつくっていける
境界をつくることは、難しいスキルではありません。
特別な人にしかできないことでもない。
むしろ、 誰もが日々のなかで少しずつ育んでいける感覚 です。
たとえば、こんなふうに問い直してみるところから始めてみてください。
この発言は、誰のためのものだろう?
いま本当に必要なのは、助けること? それとも見守ること?
「わかっているつもり」になっていないだろうか?
これらの問いは、誰かを変えるためのものではありません。
まず、自分のふるまいを見直すための問い です。
そして、自分と相手が互いに在れる「ちょうどいい距離」を探していくためのヒントでもあります。
境界の不在との在り方
境界のある暮らしが、社会の風通しを変えていく
私たちはいま、さまざまな場所で「生きづらさ」が語られる時代を生きています。
その多くが、「誰かの声が届かない」「誰かの存在が軽く扱われてしまう」ことによって起きています。
こうした構造の根っこには、 境界の不在、あるいは歪んだ境界のあり方 があると私たちは考えます。
つまり、関係性のひとつひとつを丁寧に見直していくことは、社会の空気を少しずつ変えていくための 確かな一歩 にもなりうるのです。
目に見える「成果」や「改善」ではなく、目に見えない「空気」や「信頼」に目を向けること。
それが、 関係の質を問い直すということ であり「境界のある暮らし」がもたらす本質的な変化です。
境界の感覚は、訓練でも技術でもありません。
それは、日々のふるまいのなかで、自分の選択とともに磨かれていくものです。
すぐに応えずに、少し間をとること。
相手の沈黙を、無理に埋めようとしないこと。
「自分がどう思われるか」ではなく、「相手にどう届くか」を問い直すこと。
こうしたごく小さなふるまいの積み重ねが「わかり合うこと」を焦らずに、「わかり合えなさ」も抱えながら、それでも一緒に在りつづけるという、 風通しのよい関係 を育てていくのだと思います。
境界のある暮らしは、誰かを閉め出すためのものではなく、誰かと出会いなおすためのもの。
そのことを、私たちはこれからも繰り返し、伝え続けていきます。