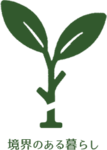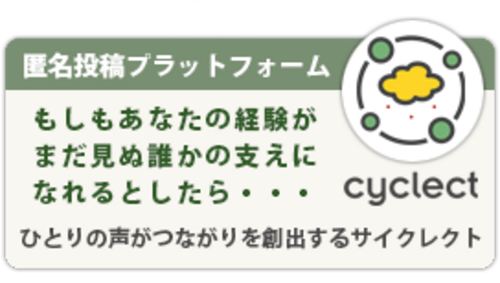- home
- 関係にひらかれた実践
関係にひらかれた実践
関係性の質を変えていく
「実践」という言葉に、どんなイメージを持つでしょうか。
誰かを助けること。社会を変えること。何かを実現させること。
そういった前向きな行動を、思い浮かべるかもしれません。
けれど私たちは「関係にひらかれた実践」という在り方を通して、実践という言葉に もう少し別の手触り を吹き込みたいと考えています。
それは 正しさや成果に回収されない、小さなふるまいの選択の積み重ね 。
たとえば、何を言うかではなく、言わないでおくことを選ぶこと。
あるいは、誰かの言葉をすぐに否定せずに、少しだけそのまま受け取ってみること。
何かを変えるためにするのではなく、 いま目の前にある関係のなかで、自分がどう在るかを問い続けること 。そこに、私たちの考える「実践」の核心があります。
正しさの外側で関係を見直す
多くの“実践”は、成果や効果を伴うものであることが期待されます。
「これをすれば、相手が変わる」
「こうすれば、うまくいく」
そんなふうに、手段と目的が直線的につながっているものとして語られがちです。
でも、関係というものは、そんなに単純ではありません。
どんなに気をつけていても、すれ違いは起きるし、沈黙は誤解されるし、正しさだけでは届かない感情がそこにはある。むしろ「正しいことをした」という意識が、 誰かを置き去りにしてしまうことさえある のです。
だからこそ私たちは「誰のためにやるのか」「それは本当に届いているのか」と問い直し続けます。
それは他者を疑うことではなく、 自分の立ち位置を見つめなおすことから始まる実践 です。
自分を整えることから始まる
たとえば、誰かの言葉に心がざわついたとき。
「それは違う」と言い返したくなるとき。
あるいは「なぜわかってくれないのか」とイライラがこみ上げてくるとき。
そうした瞬間に、自分の内側で何が起きているかを確かめてみる。
その感情は、何に触れた反応なのか。
過去のどんな体験が、いまの自分のふるまいに影響しているのか。
これは、単なる内省ではありません。
関係性の中で自分の影響を自覚することによって、はじめて変えられるふるまいがある ということ。
だから実践は、まず 自分自身を見つめる時間を取ることから始まる のです。
届けるより届くことを信じる
グラフトーンが考える実践とは「届ける」ことよりも「届くことを信じる」側にあります。
つまり、自分の想いや言葉を「伝える」ことに力を注ぐのではなく、
それがどのように受け取られるかという余白に、ひらかれているということ です。
たとえば、何か大事なことを話したあと。
すぐにリアクションが返ってこないと、不安になるかもしれません。
でもその沈黙を、無理に埋めようとせずに、ただ待つ。
その時間こそが、信頼の表れでもあるのです。
関係において本当に大切なのは、 自分が伝えたいことを言いきることではなく、相手の世界の中に自分の言葉がどう届いていくかを尊重すること 。
それは、とても静かな、けれど深い実践です。
何をするかよりもどうあるか?
実践というと、「何をするか」に目が向きがちです。
けれど本当は、「どう在るか」のほうが、ずっと関係を変えていく力を持っています。
相手の発言に違和感があったとき、どうリアクションするか。
助けを求められたとき、自分の限界をどこまで伝えるか。
関わることを迷ったとき、その迷いごと引き受けて関わりつづけるか。
そうした一つひとつの選択にこそ、私たちの在り方が現れます。
そしてそれらの選択は、必ずしも「正解」に向かうものではありません。
そのとき、その関係のなかで、自分が責任を持てるふるまいかどうか 。
そこに立ち戻ることこそが、「関係にひらかれた実践」なのです。
未完成のまま関わりつづける
実践には、終わりがありません。
いくら学び、意識していても、私たちは常に迷い、揺れ続けます。
完璧な関係など存在しないように、 完璧な実践も存在しません 。
それでも関係に関わるということは、 未完成のまま誰かの前に立ちつづける勇気 を持つことです。
「わからないけれど、ここにいるよ」と示すこと。
「うまくできないけど、考えている」と伝えること。
そうした姿勢が、 信頼や対話の土壌をつくっていく のだと思います。
誰かとのあいだにある
私たちの実践は、自分のためだけのものではありません。
同時に、相手のためだけのものでもありません。
実践とは、 自分と相手のあいだに生まれるもの です。
どちらかが我慢しすぎることも、どちらかが支配的になることもない。
お互いがそれぞれに選択できる状態であること。
その「余白のある関係性」こそが、実践によってひらかれていく世界です。
「実践」という言葉を社会に向けて語るとき、どこかで「役に立たなければ」「インパクトを出さなければ」といった圧力を感じるかもしれません。
けれど私たちは、 一人のふるまいが、関係の質を変え、それが社会の空気を変えていく と信じています。
たとえば、ある人が「黙ること」を選んだとき。
ある人が「聞きすぎないこと」を選んだとき。
そこには、操作ではなく尊重を軸とした関係の兆しが宿っています。
それは大きな変化ではありません。
でも、確かに空気を変える力がある。
実践とは、関係のなかに信頼を育てるための、小さなふるまいの選択の連続 なのです。
だからこそ、私たちはこれからも「関係にひらかれた実践」を問い続けていきます。
誰かの声にならない想いに耳を澄まし、自分のふるまいに誠実であろうとする態度こそが、この世界を少しずつ変えていくと信じて。