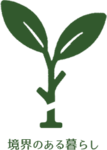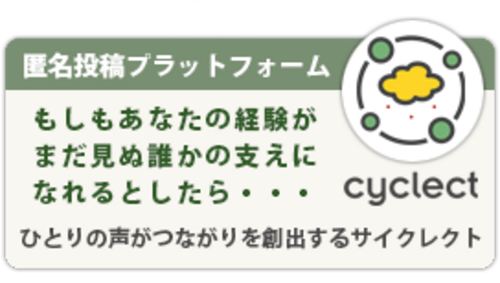- home
- 境界という思想
境界という思想
差異を保ったまま、共にあるために
分けることへのまなざしを問い直す
「境界」という言葉には、どこか冷たさや硬さを感じる人も多いかもしれません。
それは、対立や断絶、排除のイメージと結びつきやすいからです。国境、性別、役割、専門性。あらゆるところに線が引かれ、人々は分けられ、比べられ、ときに隔てられてきました。
けれど私たちは、この「境界」という概念を、単なる分断の線としてではなく、 複数のものがともにあるための媒介構造 として捉えなおしたいと考えています。
それは、互いに侵食することなく、違いのままで隣り合うための設計線。
つまり 「境界があるからこそ、共にいられる」 という視点です。
どこにでもある見えない境界
日常のなかにある境界は、目に見えるものだけではありません。
たとえば、言葉の世界と、身体の実感とのあいだ。
制度として整備された枠組みと、そこに生きる個人の感覚とのあいだ。
誰かにかけられた言葉が、自分の中に届かないとき。
「正しい」振る舞いが、なぜかうまくいかないとき。
そこには、はっきりとは見えないけれど、 確かに存在しているあいだ があります。
そしてその“あいだ”にこそ、構造の気配が潜んでいます。
私たちは、このような「説明しづらい」「言葉にしにくい」違和感を、「個人の問題」として片づけるのではなく、 感覚と思考のあいだにある構造的な境界 として捉え直します。
固定されたものではない
境界というと、動かせない線、決定的な分け目のように思われがちです。
けれど私たちが注目しているのは、 関係や文脈によって絶えず揺らぎ、調整されていくような動的な境界 です。
ある場面ではつながれることが、別の場面では不可能だったり。
ある言葉が安心をもたらす一方で、別の人には暴力的に響いてしまったり。
そんなふうに、同じ関係の中でも、線は少しずつずれていく。
それが 境界の流動性 であり、 研究の対象としての面白さ でもあります。
重要なのは、境界をなくすことではありません。
むしろ、 境界を引き直し続ける自由を持ち、その線をどこに、なぜ引くのかを問えること。
私たちは、その自由を奪われているときにこそ、違和感を覚えるのではないでしょうか。
わかりあえなさと、どう共にいるか
現代社会では「分断を超えよう」「理解しあおう」といったスローガンがよく聞かれます。
もちろん、その願い自体を否定するものではありません。
けれど、ときにそうした姿勢が、 違いをなかったことにしようとする力学 を生むことがあります。
「わかりあう」ことを目指しすぎると、 わかりあえない前提で共にいる という可能性が見えなくなってしまう。
そして、わかりあえないままに並ぶという選択が「冷たい」「無関心」「不誠実」といった評価を受けることもあります。
私たちは、この状況に問いを差し込みたいのです。
ほんとうに、理解しあうことだけが、共にあるための条件なのか?
むしろ、完全には理解しあえないという前提に立つからこそ、互いのあいだにある線を尊重し、境界を持ったままで共にいようとする態度が生まれる。
そうした関係のあり方こそが、グラフトーンの描く「共在」のイメージです。
境界は問いの発生装置
境界は、 ただそこにあるもの ではなく、 問いを生み出す構造 でもあります。
たとえば、自分の言葉が相手に届かないとき。
沈黙が続く関係のなかで「何が起きているのか」と考えるとき。
違和感があるけれど、それをどう言葉にしてよいかわからないとき。
そうした瞬間、私たちは自然と問いを立てはじめます。
「なぜうまくいかないのか?」
「どこですれ違っているのか?」
「自分はどこに立っているのか?」
そしてその問いは、構造へのまなざしを伴って、 社会や関係の設計そのものに接続されていく のです。
境界は、問題ではなく、思考をひらく起点。
それを見落とさずに捉え直すことが、私たちの研究の姿勢です。