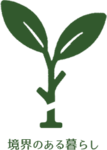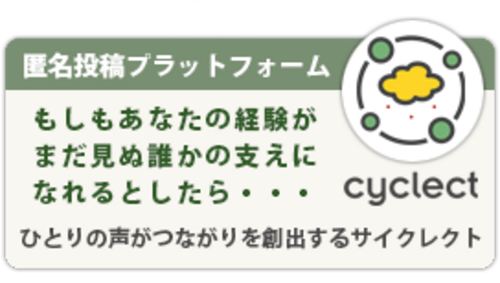- home
- 媒介と共鳴の構造
媒介と共鳴の構造
わかりきれなさに、とどまる力
わからなさが立ちあがる瞬間
誰かの語りを聞いたとき、うまく応答できないことがあります。
相手はまっすぐ話しているのに、自分の中でどこか引っかかる。
あるいは、何を言えばいいのかわからないまま、沈黙してしまう。
そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
また、制度の中で動いているとき、知らず知らずのうちに何かを判断していたり、誰かとの距離が決まっていたりする。「なぜそう思ったのか」がうまく説明できないけれど、どこかで確かに選びとっていた・・・
そういう感覚もまた、日常の中にはひそんでいます。
私たちはこうした場面にこそ、 媒介という構造が働いている と捉えています。
そしてその媒介を通じて、私たちは他者と響き合ったり、すれ違ったりしている。
その仕組みを、 共鳴の構造として読み解くこと が、この章の主題です。
媒介とは何か
「媒介」とは、異なるもの同士のあいだに立ち、何かを伝えたり受け取ったりする構造を意味します。
それは人と人のあいだだけでなく、制度と感覚、言語と身体、思考と実感のあいだなど、 あらゆる境界のあいだで働いている構造 です。
たとえば、誰かの言葉を聞いたときに生じる反応は、単純な理解や誤解だけではありません。
そこには、「こういうふうに受け取っていいのか」「自分が感じたことを言葉にしてもいいのか」といった、 無意識の翻訳や調整のプロセス が介在しています。
その翻訳は、一人ひとりの過去の経験、社会的な前提、慣習や価値観によって形づくられています。
つまり、 私たちはつねに「媒介されたかたち」で世界を受け取り、関わっている ということです。
共鳴とは何か
一方、「共鳴」とは、完全に理解しあえなくても、どこかで響きあっている感覚のことです。
それは、正確な意味の一致というより、 感覚や反応の層でつながっているという実感 に近いものです。
たとえば、誰かが語った経験に、自分の中で何かがざわつく。
言葉は違っても、「わかる」と感じる部分がある。
あるいは、逆に「どうしても言葉にならない」と思っていた自分の感覚が、別の誰かの言葉によってすくい上げられたと感じる。
そうした瞬間に起きているのが、 共鳴の現象 です。
それは、完全に一致するわけでもなく、同一化するわけでもない。
けれど確かに、 他者と交わっている感覚 が立ち上がる。
ズレに宿る構造の手がかり
媒介も共鳴も、ふだんは意識されないまま、私たちの関係や判断の中で働いています。
だからこそ、それらの構造を捉えるためには、「うまくいかなかった瞬間」や「なぜか立ち止まってしまったとき」を入り口にする必要があります。
・どうして、あの言葉は引っかかったのか
・なぜ、自分の声が届かなかったのか
・あの判断の背景に、どんな制度的前提があったのか
これらはすべて、「ズレ」の問いです。
そしてこのズレの中に、 媒介の構造と、共鳴のかたちが浮かび上がる のです。
ズレがあるということは、そこに何かが翻訳されている、あるいは翻訳しきれていないということ。
共鳴しないということは、響きあうはずの回路に何らかのノイズや断絶があるということ。
つまり、違和感や立ち止まりを観察すること自体が、 構造への入り口 になるのです。
説明しすぎないという選択
私たちは、違和感を抱えたとき、すぐに意味を与えたり、原因を明らかにしたくなります。
けれど、その態度がときに構造の複雑さを取り逃がしてしまうこともあります。
特に、媒介や共鳴といった現象は、 言葉にしすぎた瞬間に、その厚みを失ってしまう ことがあります。
だからこそ、私たちは「説明しきれなさにとどまる」ことを、ひとつの構えとして大切にしています。
わからないままで置いておく。
翻訳しきれない感覚を、そのまま観察してみる。
そうした態度が、 構造を読み替える力になる と信じています。
媒介としての関わりかた
媒介とは、なにか特別な立場の人だけが担うものではありません。むしろ、私たち一人ひとりが、常に誰かと誰かのあいだに立ち、 翻訳や橋渡しをしている存在 です。
・ある言葉を、別の言葉に言い換えて伝えるとき
・場の空気を調整するために、自分の態度を選び直すとき
・誰かの言葉が届かないときに、別の表現を探してみるとき
こうした関わりかたはすべて、媒介的な実践といえます。
そこでは、「自分がどう受け取ったか」だけでなく、「誰にどう届くか」「何が翻訳されるのか」という構造への感度が求められます。
そしてその感度は、 すれ違いや違和感に敏感であろうとする姿勢 から育まれていきます。
共鳴を設計するという視点
共鳴は偶然に起きるものだと思われがちですが、実はそこにも 構造的な設計 があります。
・どんな言葉が選ばれているか
・誰が語るか、誰に届くか
・どの文脈で語られるか
これらの要素によって、共鳴の生まれやすさ、届きやすさは大きく変わります。
つまり、 共鳴は設計しうるもの でもあるのです。
そして、何かを設計するということは、当然ながら 誰のために、何を前提に、どんな可能性を切りひらくのか という問いを伴います。
それゆえ、私たちは「響きあう」という現象をただ肯定するのではなく、その背後にある構造を問い直す必要があると考えています。
翻訳できなさにとどまる力
グラフトーンにおける「媒介と共鳴の構造」は、 関係がなめらかに進むためのノウハウ ではありません。むしろ、うまくいかなかった場面や、違和感が残った瞬間にこそ、構造の厚みと問いの源泉があると信じています。
完全にはわかりあえないけれど、共にいる。
翻訳しきれないけれど、関係がつづいていく。
その「あいだ」に立ち続けることこそが、私たちの研究の出発点です。
媒介としての関わりかたを選び、共鳴の仕組みを観察し、説明を急がず、翻訳できなさを引き受ける。
そうした姿勢の積み重ねが、 構造を読み替えるための方法 となる。
私たちは今日も、立ち止まりと違和感を抱えながら、その構造に耳をすませ続けています。