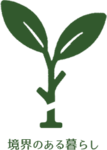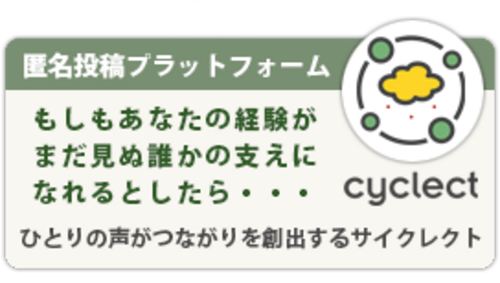- home
- 制度と実感の接続
制度と実感の接続
正しさと苦しさのあいだで、問いを立てなおす
正しいはずなのに、なぜか苦しい
「自由にしていいよ」と言われて、なぜか不自由を感じる。
「あなたのためを思って」と言われた言葉に、息苦しさを覚える。
「きちんと制度が整っているはずなのに、なぜかうまくいかない」場面に出会う。
こうした違和感は、個人の内面や感受性の問題とされがちです。
けれど私たちはそこに、 制度と言葉とが設計する世界 と、 個人の身体や感覚とのあいだにある断絶 を見ています。
制度や仕組みは「こうあってほしい」という意図や価値観を形にする手段です。
教育、医療、福祉、家族、労働——社会のあらゆる領域に制度は存在し、それらは人々の暮らしを守り、秩序を保ってきました。
けれど、その制度と、そこに生きる人間の「実感」とのあいだには、しばしばズレや摩擦が生まれます。
そして、そのズレはときに「わかっているのに、できない」「正しいはずなのに、しんどい」という形で立ち上がります。
この章では、その制度と実感のあいだに生じる断絶に目を向け、 構造の設計を問い直す視点 について考えていきます。
制度とは何か、実感とは何か
制度とは、人が人と関わるための枠組みです。
法律や組織だけでなく、「家族とはこうあるべき」「先生はこうふるまうべき」「こう言えばやさしい」といった、 共有されたふるまい や 期待 もまた制度的なものだといえます。
一方で実感とは、言葉になる前の感覚や、身体に残る反応、感情の揺れのことです。
それは制度に先んじて立ち上がることもあれば、制度によって抑圧されて初めて浮かび上がることもあります。
制度が「外側から設計された形」だとすれば、実感は「内側から立ち上がる経験」です。
この両者のあいだにズレがあるとき、私たちは違和感や苦しさを感じます。
そして、その違和感を個人の責任に帰すのではなく、 構造のズレとしてとらえ直すこと が、私たちの研究の出発点です。
なぜ「自由」が不自由に感じられるのか
たとえば、ある場面で「自由にしていいよ」と言われたとします。
けれどその「自由」が、何かを決める責任を一方的に負わされることだったとしたら?
あるいは、実際には選択肢が限られているにもかかわらず、自由という言葉だけが前面に出ているとしたら?
そのとき人は、「自由にしていい」と言われながら、なぜか動けない自分に戸惑い、苦しむことになります。
それは、制度としての「自由」と、個人の実感としての「不自由」とのあいだに、 翻訳不全が起きている ということです。
私たちは、このような翻訳の失敗や行き違いにこそ、制度の設計を見直すヒントがあると考えています。
つまり、 言葉が意図したことと、実際に届いている感覚とのズレ を手がかりに、構造の見直しを始めるのです。
わかっているつもりが生むすれ違い
制度だけでなく、言葉や常識にも構造があります。
たとえば、「ちゃんと話せば、わかってもらえる」「説明すれば、理解してもらえる」という前提は、教育や福祉の現場でもよく使われる言葉です。
けれど、話すことが苦手な人や、言葉にしにくい感情を抱えている人にとって、その前提は時に暴力的にすら感じられます。
「話せない自分が悪い」と感じさせられたり、「うまく言えなかったこと」によって、関係から外されてしまう。
こうした場面では、「わかっているはず」「わかってほしい」という善意が、すれ違いを深めてしまうのです。
私たちは、このような 言葉と実感のすれ違い にも、制度と構造の問題が潜んでいると考えています。
ズレを個人の問題として処理しない
「あなたがもっと自信を持てばいい」
「ちゃんと伝えれば、きっと伝わる」
「それは気にしすぎなんじゃない?」
こうした言葉が、制度や構造のズレを 個人の内面の問題にすり替える 場面は、日常のあちこちで起きています。
そうして、人は「もっとちゃんとしなきゃ」「自分が弱いからいけないんだ」と、自分を責めていきます。
けれど、ほんとうにそうなのでしょうか。
その人の「弱さ」ではなく、 制度や言語の側にある設計ミス の可能性はなかったでしょうか?
違和感や苦しさを、ひとりの感受性のせいにしないこと。
そこに、構造の不整合や翻訳不全があるのではないかと問いなおすこと。
それが、 制度と実感を接続しなおす第一歩 です。
接続のための構造的想像力
制度と実感のあいだにあるズレを解消するためには、「どちらかに合わせる」という発想では足りません。
「制度が悪いから壊せばいい」「感情が強すぎるから抑えればいい」といった極端な判断では、 接続の回路はひらかれません 。
私たちが求めているのは、 制度を実感に引き寄せる、構造的な想像力 です。
・その制度は、誰のために、何を前提に設計されているのか?
・その言葉は、どのような経験や文脈を想定しているのか?
・目の前の「できなさ」や「苦しさ」に、制度の側から応答する余地はあるのか?
こうした問いを立てながら、 制度の構造自体を見直し、編みなおす こと。
それが、実感に応答する制度設計の出発点です。
実感から設計を問いなおす
グラフトーンにおける研究は、現場の実感を大切にします。
それは、 制度の外側にある主観的な声 を重視するという意味ではありません。
むしろ、制度の中で見落とされがちな実感にこそ、構造のゆがみや設計の限界があらわれると考えているからです。
・なぜ、その制度では「やさしさ」が届かないのか?
・なぜ、説明しているのに、すれ違ってしまうのか?
・なぜ、「正しさ」が、人を苦しめてしまうのか?
こうした問いを、 実感という感覚の層から構造の層へと翻訳する こと。
それが、研究としての姿勢です。
構造に応答するという実践
制度と実感の接続とは、個人の理解や適応を求めることではありません。
また、制度批判を目的としたものでもありません。
それは、 構造がどのように人の実感とズレているのかを観察し、必要に応じてその設計を編みなおしていくという実践 です。
そしてそのためには、目の前の違和感をただの個人の問題として片づけず、 構造のゆがみとして見立て直す態度 が必要になります。
私たちは、「わかっているのに苦しい」場面から問いを立てなおします。
制度の言葉が届かないときに、言葉の側から変わる選択肢を模索します。
実感の声から出発し、構造へ応答していくこと 。
その往復の中に、グラフトーンが目指す「研究」の実践があります。