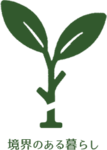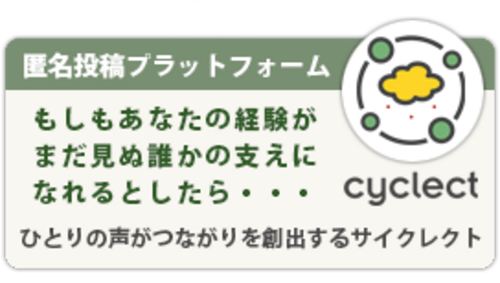- home
- 研究の実践
研究の実践
問いを抱え続けるという立ち位置から
問いとともに在る
研究と聞くと、何かを明らかにすること、ひとつの正解を見つけることを思い浮かべるかもしれません。
けれど、私たちグラフトーンにとっての研究は、そのような「知識の積み上げ」ではありません。
むしろそれは、日々の暮らしや関係の中で生まれてくる違和感や小さな気づきに、 どのように応答しつづけられるか を試す営みです。
問いに出会い、すぐに答えを求めるのではなく、 その問いとともにあることを選び直しながら生きていく 。それが、私たちの考える研究の姿勢です。
構造や制度に対する鋭い分析よりも、 自分の実感に忠実であること 。
正しさや合理性よりも、なぜか立ち止まってしまう 瞬間の意味に耳を澄ませる こと。
研究とは、思考の操作ではなく、 態度の選択である と、私たちは考えています。
構えが問いを育てる
グラフトーンには、決まった研究方法論や手順はありません。
ただし、私たちは研究を始めるにあたって、いくつかの 構え を大切にしています。
その構えとは、具体的には以下のようなものです:
・ズレをすぐに解消しようとしない
・説明しきれなさを、そのまま置いておく勇気を持つ
・他者に届ける前に、自分の実感に確かめる
・正しさの前に、立ち止まる余白をつくる
問いに出会ったとき、それをすぐに整理し、定義づけ、論理に回収してしまうと、本来の揺らぎや複雑さが見えなくなってしまうことがあります。
だからこそ、あえてすぐに結論を出さない。 未整理のまま問いと付き合う時間を持つ 。その姿勢そのものが研究なのだと、私たちは信じています。
違和感を押し流さない
研究は、何かを「わかる」ためにするものだと思われがちです。
けれど、私たちが大切にしているのは、「なぜか気になる」「ちょっと引っかかる」という感覚を、すぐにスルーせずに 足を止めること です。
違和感には、理由のはっきりしないものもあります。
たとえば、誰かの言葉がどこか不自然に感じられたり、ある制度の中で妙な息苦しさを覚えたりする。
そのとき、私たちは「自分の受け取り方が悪かったのかも」と処理しがちですが、 その感覚こそが構造への入り口 かもしれません。
グラフトーンでは、その違和感に向き合い、言葉にしようとする試みを重ねています。
そして、その言葉は「答え」ではなく、 問いの輪郭を少しずつ明らかにするための手がかり です。
実感から構造を見立てる
私たちは、「実感」を研究の出発点として扱います。
それは、論理的に整理された意見や立場とは異なり、 説明しきれない経験や感覚の層 に近いものです。
・なぜか、あのとき声が出なかった
・なぜか、その場では笑っていたけど、あとからモヤモヤが残った
・なぜか、正しいはずの制度の中で、しんどさを感じた
このような「なぜか」の集積が、 構造を問い直す視点 を生み出していきます。
私たちは、実感をそのまま絶対視したり、ただ共感を求めるために用いたりはしません。
むしろ、実感の奥にある 構造の輪郭を見立てなおすこと を目的としています。
そしてそのためには、 他者の言葉や制度の設計に無自覚に巻き込まれない感度 が求められます。
立ち止まりを肯定するという態度
問いに出会ったとき、人はつい「何か言わなければ」「動かなければ」と焦ってしまうことがあります。
けれど、すぐに動くことが、つねに誠実な応答とは限りません。
ときに、 あえて立ち止まり、沈黙の中にとどまること が、より深い問いを育てる土壌になることがあります。
この立ち止まりは、あきらめや放棄とは違います。
むしろ、それは「今はまだ、答えを出さない」という 選びなおしの意志 です。
そしてそれは、他者の思考や社会の言説に飲み込まれないために、必要な態度でもあります。
グラフトーンにおける実践とは、このような立ち止まりを含んだ、 問いとともに在る という姿勢の延長線上にあります。
往復のなかで問いを深める
研究は独りで完結するものではありません。
私たちは、 他者との関係のなかでこそ問いが深まっていく と考えています。
誰かと話すことで、思ってもみなかった視点に出会うこと。
問いを共有することで、自分の見えていなかった前提に気づくこと。
共感や同意を得ることではなく、ズレや摩擦を持ち込まれることによってこそ、 問いは育ちます。
その意味で、私たちの研究は、閉じられた思索ではなく、 関係の中で動き続ける思考のプロセス なのです。
そしてそこでは、「相手をわかる」ことよりも、「わかりきれなさを抱えながら関係をつづける」ことのほうが、大きな意味を持ちます。
わかりやすさより構造的共鳴を
私たちは、研究成果を「わかりやすく伝える」ことを目的にはしていません。
むしろ、すぐには伝わらないかもしれないけれど、 どこかで響きあう感覚をもたらす言葉 を探しています。
それは、共感でも説得でもなく、 構造的共鳴 と呼びたいようなものです。
「自分が感じていたことに、こんな形があったのか」
「ずっと言葉にならなかったものが、少しだけ輪郭を持った」
そう思えるようなかたちで、問いや気づきが他者の中にも立ち上がる。
その可能性を信じて、私たちは日々、小さくことばを置いていきます。
問いとともに立ち続ける実践
グラフトーンにとっての研究とは、「わかる」ためのものではありません。
それは、世界に対する態度であり、関係の中で問われ続ける構造への応答です。
問いをすぐに片づけず、違和感を押し流さず、沈黙を恐れず、他者との往復にひらかれ続ける。
そして、自分の実感に誠実であろうとする。
そうした小さな選択の積み重ねこそが、 私たちの研究の実践 です。
「何を知っているか」よりも、「どんな姿勢で問いと関わっているか」。
「どこに立っているか」よりも、「どのように立ち続けているか」。
わかりきれなさの中にとどまりながら、それでも世界と関係しつづける。
それが、グラフトーンが考える、研究という行為の本質です。