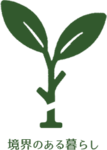- home
- 仕事・チームと境界
仕事・チームと境界
チームワークの名のもとに
「チームのために頑張る」「みんなのために支える」
そんな前向きな言葉の裏で、気づかないうちに疲弊している人がいます。
役割以上のことを背負い、時間や感情を差し出し、気づいたときには「もう限界かもしれない」と立ち止まってしまう。
チームワークは本来、ひとりではできないことを支え合うための仕組みのはずです。
けれど実際の現場では、「空気を読む」「助け合いを当然とする」「自分の感情を抑える」といった 暗黙のルールが境界を曖昧 にし、 無理の構造をつくり出していること があります。
このコラムでは、「仕事」や「チーム」という場において、どのように境界を設計することで 関係が壊れにくくなるか を、4つの視点から探っていきます。
一員という役割に埋没させない
「チームの一員として行動する」という言葉は、安心や所属感を与える反面、自分の意思を後回しにしやすい構造を含んでいます。
気づけば 「自分としてどうしたいか」がわからなくなっていく 。
これは、「個人」と「組織」のあいだにある境界が崩れてしまっている状態です。
チームでの役割と、個人としての考えは、必ずしも一致する必要はありません。
むしろ、異なる視点を保てることこそが、 チームの健全さを保つ力 になります。
境界を設けるとは、 責任放棄ではなく自分の意思と役割を切り分ける ことです。
「これは役割として必要な判断だ」
「これは自分として納得できない選択だ」
そうしたふたつの軸を保つことで、 チームのために自分を壊すリスク は減っていきます。
頑張っているからは無言の強制
職場やチームのなかで、誰かが常に忙しそうにしていたり、遅くまで残っていたりすると「自分だけ早く帰っていいのか」「あの人があれだけやってるなら、自分も…」と感じてしまうことがあります。
これは、支え合いという言葉の裏に、 感情の同調や同化を強いる構造 があるからです。 自分の選択ではなく、空気によって行動が決まってしまう関係 には、境界が存在していません。
境界を持つとは、「それぞれが、それぞれの選択をしていい」と確認できる構造を持つことです。
忙しさに引きずられず、自分のペースを決める
誰かの頑張りに感謝はしても、同じだけ背負わない
感情ではなく、仕組みで分担を再設計する
そうすることで、見えないプレッシャーによる共倒れを防ぎ、 チーム全体の持続可能性 が高まります。
助けることと奪うことは紙一重
困っている同僚やメンバーを見たとき、「代わりにやっておくよ」「自分がなんとかするよ」と助けたくなることはあります。
その行為自体は善意に満ちたものですが、境界の設計がなければ、それは 相手の学ぶ機会や主体性を奪うこと にもなりかねません。
「助けること」と「奪うこと」の違いは、 相手にどれだけ選択の余白があるか? にかかっています。
相手が求めている支援なのか
自分が先回りしすぎていないか
その人の成長や関与の場を奪っていないか
こうした確認を丁寧に行うことで、 一方的な介入ではなく、関係性の中での応答として支援 が成立します。
境界を持つとは、自分の善意を疑うことではなく、 善意がどう機能しているかを確かめながら差し出すこと です。
話し合えるチームの幻想
「オープンなチームでありたい」「何でも言い合える関係が理想」
そんな理想が語られる一方で、本音を出すと波風が立ち、黙っている方が安全——という現実もあります。
ここには 「開かれた関係=境界のない関係」という誤解 が潜んでいます。
境界とは、シャットアウトの線ではありません。
「どこまで共有し、どこからは個人として留めておくか」を調整する線 です。
すべてを話さなくても、信頼関係は築ける
本音を出すかどうかは、本人が決めるべきこと
「言う自由」と「言わない自由」の両方を守る構造があること
これが、 安全な関係のために必要な境界のあり方 です。
本音を共有できるのは、無理に引き出すことで実現するのではなく、言っても言わなくてもいいという 選択の自由が保障されている構造がある からこそです。
チームを壊すことにはならない
「もっとチームのために」「もっと助け合わなきゃ」
そんな気持ちで無理を重ねてしまうのは、 やさしさの方向を間違ってしまう構造に巻き込まれているから かもしれません。
本来、自分のペースを守ることは、チームに背を向けることではなく、 チームの一部として自分を長く保つための手段 です。
境界を引くとは、自分のエゴを通すことではありません。
誰かを傷つけないために、自分を守ること でもあります。
このコラムで紹介した視点は、すべての職場やチームにそのまま適用できる「正解」ではありません。
けれど、「なんとなく苦しい」「理由はわからないけど疲れている」というとき、関係の構造を見直すための視点のひとつにはなれるかもしれません。
チームでいることを諦めずに、その中で自分でいることも諦めないために。
境界のあるチームづくり を、ここから少しずつ始めてみませんか。