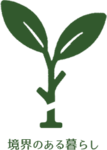わたしは、どこまでが「わたし?」
わたしって、どこまでが「わたし」なんだろう?
そんなことをふと考えるのは、きっと、日々の生活のどこかで、自分の「境界」がにじんだり、あいまいになったりしているからだと思います。
言葉にするのが難しいこの感覚は、哲学の本にはなかなか出てこない。
けれど、職場でちょっと無理して笑ったとき、家族との会話で本音を引っ込めたとき、自分の気持ちより相手の機嫌を優先してしまったとき・・・たしかにそこに、「わたしの輪郭」が関係しています。
どこからどこまでが「わたし」なのか?
「あなたはどう思う?」
「それって普通じゃないよ」
「もっとこうするべきだと思うよ」
そんなふうに、他人の言葉や期待が、自分の判断よりも前に立つことがあります。
気がつけば、自分が何を望んでいるのか、何に傷ついているのかすら、わからなくなる。
わたしの中にあるものなのに、わたしの意思で扱えない・・・そんな違和感。
誰かの価値観を優先することに慣れすぎてしまうと、「これはわたしの問題だ」と線を引くことすら、怖くなってしまう。
それでも、心のどこかでは小さな声が言っています。
これは、ほんとうの「わたし」じゃないと。
境界を引くということ
「境界」とは、誰かと距離をとるためのものではなく、 自分と向き合い、守り、そして関係を持続可能にするための輪郭 のことです。
それは、とても静かで、目には見えにくい。
たとえば、こんなふうに日々の中にあるものです:
* 誰かに誘われたけれど、今日は断ろうと思えたとき
* 期待されているけれど、「無理をしない」と決められたとき
* 頼まれごとに「考えさせてください」と返したとき
それは、対立でも拒絶でもありません。
「わたし」を大切にしながら『あなた』と関係を結ぶ方法です。
なぜ、線を引くことが怖いのか?
線を引くことに、罪悪感を覚える人は少なくありません。
それはきっと、子どもの頃に「がまんできる子がえらい」と言われたり、「わがままはダメ」と言われて育ったからかもしれません。
自分の気持ちを最優先にすることは、「わがまま」や「自分勝手」と言われてきた。
だから、他者を優先しすぎて、自分の声が聞こえなくなる。
けれど、 自分の声を聞き取れないまま、他人と向き合うことはできません。
他人の境界を尊重するためにも、自分の境界を知ることは欠かせないのです。
哲学と暮らしのあいだで考える
哲学の世界には、「自他の区別」や「自己とは何か」といった問いがあります。
けれどこの場所で大切にしたいのは、 その問いを日々の暮らしの中で、実感をともなって考えてみること です。
*あの一言にモヤモヤした
*うまく断れなかった
*人と一緒にいると、なぜか疲れる
そんな体感を起点にして、そこにどんな境界があったのか、どんなふうに輪郭をにじませていたのか・・・
暮らしのなかに問いを持ち込むと、哲学はもっと小さく、やわらかく、使いやすくなる。
ここは、そんなふうに 哲学と実践のあいだにある小さな場所 でありたいと願っています。
それでも、わたしをわたしのまま扱う
人と深くつながることは大切です。
でも、そのために自分を削る必要はありません。
全部をわかってもらう必要もない。
「共感」よりも、まず「共存」を。
相手の中に入らずに、となりに立つ。
> わたしは、どこまでが「わたしで、
> どこからが「あなた」なのか。
その問いを忘れずにいれば、関係が少しずつ、やわらかく変わっていくように思います。
問いの余白
*「それ、私もそう思うよ」と言われたとき、あなたは安心しますか?
それとも違和感がありますか?
*他人の感情に巻き込まれて、自分を見失った経験はありますか?
*「それはあなたの問題」と言えたことがありますか?
それはどんな状況でしたか?