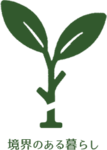「つながる」と「守る」は矛盾するか?
境界線とやさしさの再定義
「大切にしたい人がいる」
「わかり合いたいと思っている」
そんなとき、人は自然と「距離を縮めよう」とします。
言葉を交わし、時間を過ごし、相手の世界に足を踏み入れていく。
そして、知らないうちに 「踏み込みすぎてしまう」 ことがあります。
それが親密さの代償のように感じられる関係も、あるかもしれません。
でも本当に 「守ること」と「つながること」は矛盾しているのでしょうか?
誰かと深く関わりたいと思ったとき、わたしたちは自分を犠牲にしなければならないのでしょうか?
境界を引くと「冷たく」なる?
たとえばこんなことがあります。
*自分の時間を確保するために誘いを断った
*話を最後まで聞かず、「それは私にはできない」と言った
*相手の感情に巻き込まれず、落ち着いて距離をとった
こうした行動は、時に「冷たい」と受け取られてしまうことがあります。
「相手のために」動くことを美徳とする文化の中では、
自分の境界を守ること=利己的
という構図が強く刷り込まれています。
でも、本当にそうでしょうか?
自分を守らずに誰かを守ることは、できるでしょうか?
相手に寄り添いたいと思いながら、自分が疲弊していっては、関係は長く続きません。
ここにいる、でもすべては受け止めない
境界とは、「ここまでがわたし、ここからがあなた」という線です。
でもそれは、遮断するための壁ではありません。
むしろ、
関係を可能にする前提
とも言えます。
「ここまでは入っていいけれど、そこから先は大切にしたい」
「あなたを受け止めたいけど、わたし自身も尊重したい」
そう思える関係は、お互いにとって やさしくて健やか です。
たとえば誰かの怒りや不安に触れたとき、自分までその感情に飲み込まれてしまわないよう、一歩引いて「そのまま受け取らない」という選択があっていい。
それは拒絶ではなく、「あなたを見失わずにいる」ための態度です。
境界のある関係は、あたたかい
「親しい」ということと「近すぎる」ということは違います。
本当に親しい関係は、言わなくても察するのではなく、言えること、断れること、気持ちを尊重できることの積み重ねです。
境界のある関係とは、こういうものかもしれません:
*何でも話してほしいけど、話したくない日は話さなくていい
*心配しているけど、手出しはしない
*気になるけど、相手の選択を信じて待つ
それは、お互いに「孤立」しないでいる方法であり「自立」したまま手を取り合うような感覚です。
「守る」ことは、関係から降りることではない
境界を引くことを、「距離を置くこと」と捉えると、関係を終わらせるような響きを持ってしまうかもしれません。
でも本当は、「関係を壊さないように、静かに線を引く」こともあるのです。
*言いたいけれど言わない
*聞かれても答えない
*助けたいけれど、助けない
それらは、関係を大切にしたいという願いからくる判断かもしれません。
近づきすぎてしまうことでしか愛せないなら、それは誰かを支配する愛に変わってしまうこともある。
だからこそ、「守る」と「つながる」は同時に叶えられるものだと、この場所では信じたいのです。
哲学と実践のあいだにある線引き
哲学的には、「関係性の中にある自律とは何か」「共在とは何か」という問いにつながります。
でも、ここで立ち止まりたいのは、もっと日常的な瞬間です。
*LINEの既読をすぐ返さなくてもいいと決めたとき
*子どもが泣いても、まず深呼吸してから向き合うとき
*パートナーの悩みに、解決策を出さずにただ隣にいるとき
そんな場面で、わたしたちは「関係を壊さずに、自分を守る」練習をしている。
それこそが、境界を生きるということかもしれません。
つながりのかたちを、問い直す
> 境界があるから、壊れない関係がある
> 境界があるから、深く理解しようとできる
このコラムでは「距離をとること」を悲しみや諦めとしてではなく、 あたらしいつながりのかたち として捉え直してみました。
「ちゃんとわかりたい」から、「ちゃんとわかれなくていい」へ。
そんなふうに関係の定義を柔らかくできたとき、きっと「わたし」も「あなた」も、もう少し息がしやすくなるはずです。
問いの余白
*距離をとったことで、関係がうまくいった経験はありますか?
*「近すぎる」と感じるとき、あなたの中で何が起きていますか?
*境界を引いたことで、自分を守れたと思えた瞬間は?