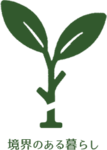境界がない関係は、なぜ苦しくなるのか?
「わかってほしい」が絡み合うとき
人と人とが深くつながろうとするとき、「理解したい」「受け止めたい」という気持ちはとても自然なものです。
でもその思いが強くなりすぎると、気づかないうちに 境界が溶けてしまう ことがあります。
*相手の気分に左右される
*相手の問題なのに、自分が責任を背負ってしまう
*相手の沈黙を「自分のせい」と思ってしまう
こうした感覚が続くと、関係はだんだんと苦しいものになっていきます。
「境界のない関係」は、一見やさしさに包まれているようで、実は互いの輪郭を失わせてしまう危うさを含んでいるのです。
境界がない関係のなかで、起こること
わかりやすく言うならば、それは 「混線」 です。
*誰の怒りかわからなくなる
*誰の不安かわからなくなる
*どこまでが自分の役割なのかわからなくなる
相手の痛みが、まるで自分の痛みのように感じられることはあるでしょう。
でも、それをそのまま背負ってしまうと、「どちらの問題なのか」が見えなくなり、 関係は重たくなります。
これは、親子、恋人、同僚、友人──あらゆる関係性に起こりえます。
そして厄介なのは、この「混線した状態」が、とても「いい関係」のように見えてしまうことです。
「わかってくれるはず」が苦しみを生む
境界のない関係においては、「わかってくれるよね」「察してよ」「言わなくても気づいてよ」という 無言の期待 が生まれやすくなります。
けれど、期待はことばにしなければ、ただの プレッシャー になってしまう。
そして、それに応えられないとき、「どうしてわかってくれないの?」という怒りや寂しさが生まれる。
わかってもらえないことへの痛み、わかろうとしても届かないもどかしさ。
境界がない関係ほど、わかり合えなかったときの 衝突は深く なります。
わかりすぎないことの知恵
「相手を理解したい」と思うことは悪くありません。
でも、 わかろうとしすぎないという知恵 もまた、大切です。
それは、相手のことを諦めるのではなく、 相手の中に、自分が踏み込めない領域があると認めること。
そして、自分の中にも、相手には踏み込ませない部分を大切にすること。
たとえば、こんなふうに考えてみてもいいかもしれません:
*「わたしにはわからないけど、それでもそばにいる」
*「その選択の理由は知らないけど、尊重したい」
*「共感はできなくても、聴くことはできる」
それが、境界を保ちつつも、関係を続けていくための方法です。
あなたの気持ちと、わたしの気持ちを分ける
境界がある関係では、「それはあなたの問題だね」と言うことができます。
冷たく聞こえるかもしれないけれど、それは 責任を分けて持つということ。
*誰の問題かをはっきりさせる
*自分が対応すべきことを自覚する
*そのうえで、どう関わるかを選ぶ
このプロセスがなければ、関係はどちらかが背負いすぎて壊れてしまう。
逆に言えば、「それはわたしの問題なんだ」と気づけたとき、相手を責める代わりに、自分の選択に立ち戻ることができるのです。
「ひとつになる」ことを手放す
「ふたりでひとつ」
「親だからわかるはず」
「夫婦なら、気づいて当たり前」
こうした言葉には、いかにも“近しい関係”らしさが宿っています。
でも、そうやって 自他の境界を失わせていく関係 は、どこかでひずみを生みます。
graftone という名前には「接ぎ木」そして「ひとつになる」という意味が込められています。
けれど、それは「混ざる」ことではありません。
違うまま、並ぶ。
切り離されたまま、支え合う。
だからこそ、「わたし」と「あなた」のあいだに線が必要なのです。
境界をもつことで、見えてくるもの
境界があるからこそ、「相手のことを想像する」という動きが生まれます。
見えない部分に敬意を払い、わからない部分に耳をすませる。
すべてを知ろうとしないから、関係は長く続くのです。
むしろ、 わからないまま、共にいる という選択こそが、今の時代に必要な信頼のかたちではないでしょうか。
問いの余白
*「わかってほしい」という気持ちが強くなりすぎて、関係が苦しくなったことはありますか?
*誰かの問題に必要以上に巻き込まれてしまった経験はありますか?
*「わかり合えなくても、一緒にいられる」関係は、ありますか?