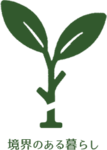子どものころ、線を引かせてもらえなかった
境界感覚の後育てという視点
子どもだったわたしは、「いい子」として扱われるたびに、少しずつ「線を引く感覚」を手放していった気がします。
たとえば、こう言われたことはありませんか?
*「そんなこと言ったら、お母さん悲しむよ」
*「先生に逆らうなんて、どういうつもり?」
*「お兄ちゃんなんだから、譲ってあげなさい」
小さな反発、違和感、戸惑いのサインはあったのに、大人たちの正しさや期待の前で、それをことばにする術は教えてもらえなかった。
線を引くことを、許されなかった
子どもの頃のわたしたちは、「嫌だ」「やめて」「もういい」と言いたい場面に、たくさん出会っていたはずです。
でもそのとき、周りの大人はそれを 「わがまま」として否定したり、「ちゃんとしなさい」と上書きしたりした かもしれません。
その結果、こういう感覚が身体に染みついていく。
*自分の気持ちより、相手の感情を優先する
*拒否すると嫌われる、という恐れ
*「がまんできること」が愛される条件
そうして、 他者との間に線を引くという感覚を、体験的に学べなかった のです。
本当は、線を引いてよかった
もしもあのとき、「イヤ」と言うことを許されていたら、きっとわたしたちは、もっと健やかに境界を持てる大人になっていたかもしれません。
けれど現実には、「嫌」と言えなかった過去があり、「我慢が正しい」と信じ込んできた歴史があり、「期待に応えなければならない」と刷り込まれた習慣があります。
でも、過去に境界を学べなかったからといって、 一生そのままではない。
わたしたちは、大人になってからでも、 「線を引き直すこと」ができる。
境界を引くという「後育て」
「もう子どもじゃないんだから」と言われがちですが、 境界を持つという感覚においては、今も「育て直している最中」のわたしたち が、たくさんいます。
それは、こんな小さな練習から始まります。
*「それ、今はできません」と言ってみる
*何かを断ったあとに、自分を責めすぎない
*疲れているときに、返信を遅らせることを自分に許す
*相手の期待に応えないことが、「関係を壊すこと」ではないと知る
最初は罪悪感がついてまわるかもしれません。
でも、それでもいい。
境界を持つことは、誰にとっても「後育てできる感覚」 なのです。
境界を持つことは、自分を信じ直すこと
子ども時代に境界を育てられなかった背景には、「自分の感覚を信じてはいけない」と教えられてきた経験があります。
だからこそ、いまわたしたちがしようとしているのは、 「自分の内側にある感覚を、信じ直す」こと。
*ちょっと違和感がある
*なんだか落ち着かない
*無理して合わせている気がする
それらの小さな信号に、ふたをしないこと。
他人の評価よりも、まず 自分の感覚を一番信じること。
そこに、境界の芽が宿ります。
「昔そうだった」ではなく「今どうしたいか」
大人になったわたしたちは、自分の生き方を選び直せます。
過去に線を引かせてもらえなかったとしても、いま どんな線を引きたいのか は、自分で決められる。
*もう少し静かな関係を選んでみたい
*気持ちのいい距離感を探してみたい
*境界を持って、でも関係をあきらめない方法を考えてみたい
そのすべての選択肢が、いまここにあります。
問いの余白
*子ども時代、「線を引けなかった」と感じる場面はありましたか?
*いまの自分が「もう一度、線を引き直したい」と思っている関係はありますか?
*境界を持つために、まず“自分に許したいこと”はなんですか?