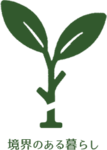言わないことで、伝わることもある
「沈黙」は、育てるための線引き
「何度言ってもやらない」
「ちゃんと伝えてるのに、聞いてくれない」
「また怒ってしまった…」
子どもとの関係で、そんなふうに思ったことのある方は、きっと少なくないと思います。
子育ては、どうしてこんなに「伝えること」に悩むのでしょうか。
もっと分かってほしくて、もっと正しく育てたくて、気づけば、わたしたちは言葉をたくさん使いすぎてしまいます。
でも、ほんとうに必要な言葉は、そんなに多くないのかもしれません。
ときには 「言わない」ことが、いちばん深く伝わる手段になる こともあるのです。
言葉が多すぎると、届かなくなる
たとえば、朝の支度でバタバタしているとき。
なかなか着替えない子どもに、ついこう言ってしまう…
「早く着替えて」
「また遊んでるの?もう時間ないよ」
「何回言ったら分かるの?」
言っていることは正しい。
でも、声のトーンも、言葉の勢いも、 子どもにとっては「責められている」と感じる ことが多いのです。
そうなると、子どもはどうするか。
返事をしなくなる。
別の話題にすり替える。
あるいは、わざと反抗的な態度をとる。
実はこれ、「怒られている内容を理解していない」のではなく、 理解しようとする余裕がなくなってしまっている のです。
「言わない」とは、放棄ではなく「選択」
「じゃあ、言わないってどういうこと?」
それは、 子どもにすべてを任せて放っておく 、ということではありません。
むしろ逆で 「いま言わなくていいこと」を選ぶ という、大切な判断です。
たとえば:
◎一度だけ伝えて、あとは静かに見守る
◎言いたくなったとき、いったん深呼吸をして黙る
◎子どもが自分で気づくまで、待ってみる
それはまるで、「境界線を一歩うしろに引く」ような感覚です。
子どもとの距離をほんの少しだけ広げて、そこに 自分で気づく余白 をつくる。
この余白があることで、子どもは「自分で考える力」をすこしずつ育てていけます。
境界を持つことは、子どもを信じること
「言わない」という選択をすると、はじめはとても不安になります。
「ちゃんと伝えなきゃ育たないんじゃないか」
「サボるクセがつくんじゃないか」
「わたしが無責任に見えるんじゃないか」
でも、実際にはその逆です。
言葉で手を出しすぎないことは、信頼のあらわれ です。
自分でできるようになることを信じて、自分の感情を処理できる力を信じて、そっと待つ。見守る。沈黙する。
それは、親の「諦め」ではなく、「ちゃんとあなたの力を信じているよ」という、静かなメッセージなのです。
今日からできる、小さな実践
では、実際にどんなことから始めてみればよいのでしょうか。
「言わない」子育てを、日常に取り入れるためのヒントをいくつか紹介します。
一度だけ伝えて、それ以上は繰り返さない
「お風呂に入る時間になったよ」
→ それ以上は言わず、次の行動を待つ。
→ どうしても動かないときだけ、「じゃあ、あと5分後に声をかけるね」と静かに予告。
口を閉じたまま、寄り添う
不機嫌な子にアドバイスせず、ただ隣に座る。
「なんで怒ってるの?」ではなく、黙ってそばにいる時間をつくる。
「いまは伝えない」と決める時間をもつ
寝る前・朝の出発直前など、伝えても届きにくいタイミングは「言わない時間帯」として意識する。
最後に
子育てには、言葉が必要です。
でも、ときには「沈黙」こそがいちばん深いことばになることがあります。
境界を引くというのは、冷たくなることではなく、 伝えるべきことと、いまは伝えないでおくことを、選び取るという姿勢 です。
子どもとぶつかってしまった日、自分の声に疲れてしまった日、よかったら思い出してみてください。
きょうは、「言わない」を選んでみる。
それでも、ちゃんと伝わることもあるから。