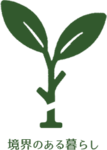伝えたいのに伝わらない
何かを教えるとき、何かを伝えようとするとき、
「ちゃんと話したのに、伝わっていない気がする」
「反応が薄くて、わかってくれたのか不安になる」
「どうしたら届くんだろう……」
そんなもどかしさを感じたことはありませんか?
相手が子どもでも、生徒でも、部下でも、あるいは家族や、対話の場にいる誰かでも…
「伝える側」に立つときに感じる悩みは、案外よく似ています。
でも、その「伝わらなさ」は、本当に相手が悪いわけでも、あなたの伝え方が間違っていたわけでもないかもしれません。
もしかしたらそこには「もっと伝えなきゃ」「ちゃんとわかってもらわなきゃ」という焦りが、少しだけ前に出ているのかもしれません。
伝えることと、踏み込みすぎないこと
誰かに何かを教えるとき、わたしたちは「伝えること」に集中しすぎて、知らず知らずのうちに、相手の領域に踏み込みすぎてしまうことがあります。
でもほんとうは、すべてを伝えきらなくてもいいのかもしれません。
相手には相手のタイミングがあり、受け取り方があり、どこまで入ってきてもらうかは、その人自身が決めることでもあるからです。
だからこそ、「これくらいで、いったんやめておこう」と思える距離感。
それが、伝える側にとっての境界になるのだと思います。
実践ヒント:伝えきらずに、残しておく
相手の中に残るものは、ときに「わかりやすい説明」よりも、すこし余白のある言葉かもしれません。
◎一度だけ説明して、あとは待ってみる
◎「どう思った?」と先に問いかける
◎「あなたなら、どうする?」と主導権を渡してみる
子どもには「自分で考える余地」を。
生徒には「試してみる時間」を。
部下には「自分で責任を持つ体験」を。
すべてを伝えきらないということは、相手の中に、変化が生まれる余地を残すことでもあります。
境界は、信じるというかたちの関わり
伝えることに一生懸命になると、つい「もっとちゃんと教えなくては」と思ってしまいます。
でも、言いすぎないこと。踏み込まないこと。
それは冷たさではなく、信頼のかたちなのかもしれません。
「ここまで伝えたら、あとは待つ」
「その人の内側で、育つ時間を信じる」
関わることと、踏み込みすぎないことのあいだに、教育や学びにとっての大切なバランスがあるのだと思います。