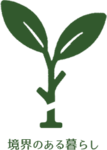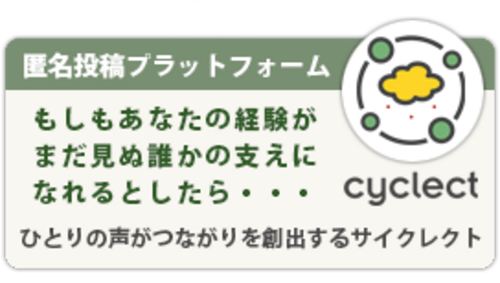- home
- 研究領域
研究領域
グラフトーンにおける研究とは、単なる知識の集積や理論の構築ではありません。
日々の暮らしのなかで ふと立ち上がる違和感 や、 言葉にならない感覚 を出発点に、 社会の構造や制度との接点を見直す ための思考の試みです。
現代社会において、私たちは多くのものを「制度」や「仕組み」として共有しています。
教育、医療、福祉、家族、労働といった枠組みは、正しさや効率を前提として設計され、一定の秩序や安心を与えてくれます。
けれどその一方で、 見えない不自由さや、こぼれ落ちる声 を生み出すこともあります。
その制度と感覚、構造と体験とのあいだには、ときに深い断絶が生まれます。
たとえば「自由にしていいよ」と言われて、なぜか不自由を感じるとき。
あるいは、「説明できないけれど、どこか苦しい」と感じる場面。
そうした感覚は、 個人のわがまま として処理されがちですが、私たちはそれを、 構造を問い直す入り口 だととらえます。
問いを立てることは、 社会の設計に応答する態度 でもあります。
ただし、問いを立てたときに、すぐに答えを出そうとしすぎると、既存の価値観や他者の枠組みに巻き取られてしまうことがある。
だからこそ、 ときに答えを急がず、留まることを選ぶ ・・・
その姿勢そのものが、構造を読み替えていく力を持つと、私たちは信じています。
違和感を、そのまま流さないこと。
その意味や背景を掘り下げ、社会のどこにどんな設計がなされているのかを見抜くこと。
そしてそれを、自分の中にとどめておくだけではなく、 他者と共有可能なかたち に編みなおしていくこと。
それが、私たちの考える「研究」です。
1. 境界という思想
私たちは「境界」を分断ではなく、 異なるものが共にあるための設計線 としてとらえています。それは固定された線ではなく、関係や文脈によって揺れ動く、 変化し続ける構造 です。
たとえば、制度と実感、言葉と沈黙、個人と他者のあいだ。
そうしたあいだに生じるズレや摩擦にこそ、見えにくい構造の気配があらわれます。
私たちは、こうした違和感を、個人の問題として片づけず、 感覚と思考のあいだにある「境界」 として見つめなおすことから研究をはじめます。
わかりあえなさを前提に、線を引きなおすこと・・・、その実践のなかに、 対立でも統合でもない、あたらしい共在のかたち があると信じています。
2. 媒介と共鳴の構造
媒介とは、異なる立場や世界の「あいだ」に立つこと。
共鳴とは、完全に理解しあえなくても、どこかで響きあう感覚のこと。
私たちは、こうした あいだに生じる接続やずれを観察すること から、研究を始めています。
たとえば、他者の語りに触れて生まれる小さな揺れや、制度が判断に及ぼす見えない影響。
そうした違和感には、 構造的な媒介の働き が潜んでいます。
その媒介装置や共鳴の仕組みを、ズレや行き違いを手がかりに捉え直す。
そして、「なぜ届かなかったのか」「なぜ立ち止まったのか」と問いなおす。
すぐに答えを出さず、 説明しきれなさにとどまること 。
そこに、構造を設計しなおすための入口があると、私たちは考えています。
3. 制度と実感の接続
制度とは、社会の中で「正しさ」や「安心」を形づくる仕組みのこと。
教育、福祉、医療、働き方といった枠組みがそうです。
一方で実感とは、その制度の中で人が感じている 違和感やひっかかり 、 うまく言葉にできない感覚 のこと。
私たちは、この 制度と言葉とが設計する世界 と、 身体や感情の実感とのズレ に注目します。たとえば、「自由にしていいよ」と言われて、かえって不自由を感じることや「わかっているつもり」が、すれ違いを生んでしまうことなど、こうした摩擦は個人の問題ではなく、 構造のズレが生み出している 可能性があります。
そのズレを見つめなおすこと。
そして、制度の側から設計を変え直す視点を持つこと。
それが、グラフトーンの考える「研究」のひとつのかたちです。
4. 研究の実践
グラフトーンの研究には、決まった方法論や手順はありません。
けれど、いくつかの 構え があります。
たとえば
ズレをすぐに解消しようとせず、 そのまま観察しつづけること 。
意味を決めすぎず、 説明しきれなさに言葉を選ぶこと 。
問いに出会ったとき、他者に届ける前に、 自分の実感に確かめること 。
問いには、もちろん応答していきます。けれど、答えを急ぎすぎると、既存の構造や言説に巻き取られてしまうことがある。だからこそ、 あえて立ち止まる自由を持つ ・・・その判断自体が、構造を見直す態度につながります。
研究とは、思考を動かすだけでなく、 関係や構造に働きかける行為 でもある。
その選択の積み重ねが、私たちの実践です。
わかることではなく、どう立ち続けるか
グラフトーンにとって、研究とは世界を「わかる」ための手段ではありません。
違和感を 見過ごさずにとどまり 、 構造を観察 し、関係を設計しなおしていくための 応答のしかた です。
答えを持ちながらも、 どう問い続けられるか 。
共感することよりも、 どう違いのまま共にあれるか 。
私たちは、説明を目的とせず、感覚や関係の奥にある構造を見立てなおす態度を探っています。
わかりあえなさを恐れず、立ち止まる勇気を持つこと。
自分の実感を、社会の設計へとつなぎ直していくこと。
そうした実践のひとつひとつが、未来の関係のかたちを問いなおす入り口になると信じています。